困ったらとりあえず「御供」で
百貨店にはいろいろなお客様がみえます。
目的も手段も方法もはっきりしている方
目的も手段もはっきりしているのに、
方法がみえない方。
特に弔事の贈り物に多いようです。販売員の腕の見せ所です。
弔事で迷ったら「御供」にすべき理由
「御供」はそもそもどういうときに使うのか
品物にしかつかない
基本的には弔事の言葉です。
どなたかが亡くなったときに
現金を渡すときは「御霊前・玉串料・忌慰料(宗教によって違います)」
品物を渡すときは「御供・奉献」
法事や周年祭の時に
現金を渡すときは「御佛(仏)前・玉串料・御花料」
品物を渡すときは「御供・奉献」
品物を渡すときはどういうシチュエーションか宗教なのかにかかわらず、
「御供」で持っていくことができます。
この段階でもうオールマイティなのだということは、
お分かりいただけると思います。
注意すべきことは
返礼の品物には使えないということでしょうか。
返礼の際の掛け紙(のし紙)は、
東日本仏式なら「志」
西日本仏式なら「粗供養(場合によっては満中陰志)」
神式なら「偲び草」
キリスト教カトリックなら「偲び草・(場合によっては昇天記念)」
キリスト教プロテスタントなら「偲び草・(場合によっては召天記念)」
となり、「御供」は登場しません。
よくよく考えると
返礼をもらった側はご不幸事があるかないかといえば、
おそらくないわけで御供をする必要がないのですから、
掛け紙(のし紙)には故人を弔うためにわざわざ来てくれたお礼なり感謝の気持ちを
伝えるのが自然です。
「御供」と「御供物」の違いは?
違いはほぼない
言い方の違いといいましょうか。
読み方はまるっきり変わってしまいますけれども、
「御供」 -ごくう・おそなえ
「御供物」-おくもつ・おそなえもの
という読み方をします。
色々な説があります
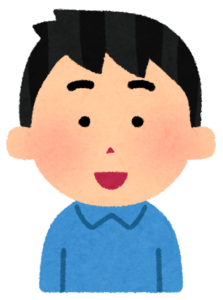
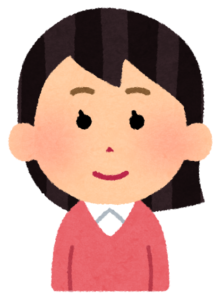
という風にも言われていますが裏がとれていません。
未確認情報としておいてください。
というわけで違いはほぼないと思った方がよさそうです。
カザマツリはこの話をするとき大体の場合は

と言っています。
それでも気を付けることは?
冒頭の話
どういう贈り物か確認する必要がある
買い物にみえた方が何を目的にどういうものを買いに来たのか。
それが説明できない方って結構多いんですね。
- 何が起きたのか
- 品物だけ持っていくのかほかに何かあるのか
- いつ
- どこで
- 誰から
- 誰に渡すのか
これをはっきりさせる必要があります。
- 友人の父が亡くなった
- お香典は持って行かない
- 四九日法要が終わった
- 友人のお宅で
- 私から
- 友人に渡す
これに当てはめると、
ということになります。現金と品物をまとめて差し上げるなら現金だけ掛け紙が付きます。
なので「ご仏前」の香典袋を掛け紙なしの品物の上にのせて渡します。
この渡し方を「お盆代わりにしてお渡しする」と言います。
ただこの場合は品物だけなので「御供」の掛け紙(のし紙)を掛けます。
正しくはどうするかわからないけれど、多分違う。
お店に差し上げものを買いに来るわけですから、
現金に何をつけるかとかは気にする必要はないわけです。
品物だけ気にすればいいのですが、
- 90代の母の友人が亡くなったらしい
- お香典はどうするかわからない
- いつ亡くなったかわからない
- その方の家に行くんじゃないの?
- 母は高齢だから持っていけるかな
- 私は買ってくるよう言われただけ
ほぼ何をしに行くのかよくわからないのですが、
おそらくお仏壇にお供えするのだろうから「御供」の掛け紙を勧めたところ、

こうなっちゃうとどうすることもできないんですね。
昔いましたね。小学校でお楽しみレクリエーション大会で、
クイズ大会するとクイズの答えにいちゃもんつける子。

もうどうすることもできなんですね。
何の話をしているんでしょうか。
この方の場合は結局持っていくんだか持っていかないんだか、
お仏壇にお供えするんだかしないんだかもわからないため、
貼らないでクリアフォルダーにあり得る掛け紙(のし紙)をすべて入れて、
用途に応じてご自分で掛けていただくということになり、
どういう場合ならどの掛け紙(のし紙)というメモとともに、
お持ち帰りいただきました。
で、どうすればよいのか
- 弔事なのかどうか
- 返礼でないかどうか
- 品物に付けるかどうか
- どこにお住まいの方に贈るのか
あとは東日本なら黒白、西日本なら黄白というのを間違いないようにすれば
問題ないでしょう。